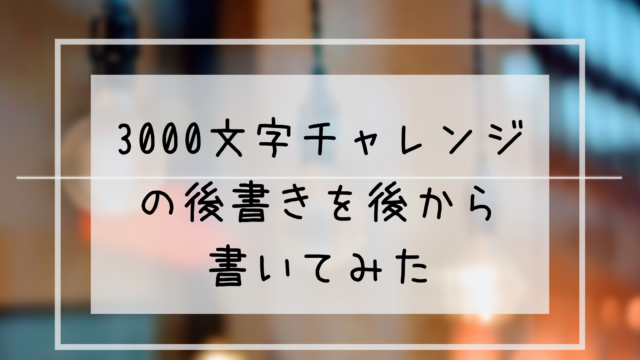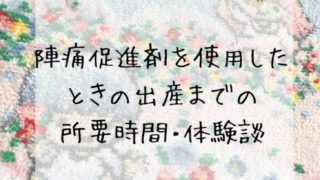ピピっピピっピピっピピっ!
パシっと目覚ましを止める。
あなたは、熊のようにゴーゴーとイビキを隣でかいている。
そろそろ、揚げパンの仕込みを始めなければ。昼寝しすぎてしまった。
起き上がろうとすると、膝と腰が痛む。
「アタタタ・・」
起き上がってしまえば、少し経てば痛みは遠のく。
「あなた、そろそろ子ども達が来る時間ですよ」
「ガッ!?・・そうか、起きる時間か」
あなたは顔をザブザブと洗うと、さっさと調理場へ向かう。
私もならってザブザブと顔を洗ってから、ホウキとちりとりを持って店に向かう。
「揚げパンは俺が担当だからな」
いつだかそう、あなたが言ってから揚げパンはあなたが担当になった。
私は開店前に店の床にちらばっているほこりをかき集める。
少しすると、たっちゃんが店のドアを勢いよくガラガラ!と開けた。
「おばちゃん!新しいカード来た!?」
「うん、来たよ。これでしょ?」
「やったー!入るの遅いよー!」
「しょうがないよ。入荷が遅れてたんだ。はい、1枚100円ね」
たっちゃんはポッケに右手をつっこむと100円を取り出して、私の手に渡した。
「ありがとね」
カードをたっちゃんは選ぶと、勢い良く飛び出していった。
私達が住んでいるところは子ども達がとても多い地域で、今も小学校でまだ1学年3クラスはある。
賑やかな小学校のすぐそばに、こぢんまりとした駄菓子屋をオープンしたのはもう5年も前のことだ。
ささやかな軍資金でも購入できる、小さな居抜き物件を選んでいた。
駄菓子屋を始めてみて、うまい棒もキャベツ太郎もコーンポタージュも、まだまだ現役なことに驚く。
子ども達があまり来ない雨の日には、少し駄菓子をつまむこともある。
10歳くらいの頃よく食べたあの頃と、味は全然変わらない。やっぱり、美味しい。
ガラガラっ!
今度はさよちゃんだ。
「おじちゃん、揚げパン1つくださいな」
「まだアツアツだから、気をつけてな。1個100円ね」
ガサガサする紙に揚げパンをくるんで、あなたはさよちゃんに揚げパンを手渡す。
「熱いよー!」
「だから、熱いって言ったろう。冷めてから食べな」
「うん。はい、100円」
さよちゃんがふくふくした手のひらに握った100円を差し出すと、あなたのしわしわの手が受け取る。
「私も揚げパン一つ食べて良いですか?お腹が減っちゃって」
「いいけどな、熱いぞ」
「わかってますよ」
ガサガサの紙に包まれた揚げパンは、受け取るとふうわりとした柔らかさだ。
ザラメのような細かな砂糖がパンの表面を綺麗にくるんでいる。
バク!と一口食べてみると、やっぱり熱い。でも、ほわほわとした食感の揚げパンが本当に美味しい。
「美味しいですねぇ」
「そりゃそうだ。俺が作ってるんだから」
「そうでした」
パクパクと揚げパンを食べる。
気が付くと、あなたも隣の椅子に座って揚げパンを頬張り始めた。
「腹が減ったからな」
それから何人かの小さなお客さんの相手をした後に、カラカラと静かに店の扉が開いた。
なずちゃんだ。
「あら?どうしたの?」
10歳になったばかりのなずちゃんは、私達の初孫だ。
娘は2つ向こうの駅に住んでいるから、なずちゃんがこの店に来るときには大抵家族皆でやってくる。
1人だけでこの店へ来たのは初めてだ。
「何かあったの?」
「ううん、なんもない。揚げパン食べに来たの」
「なんだ、揚げパンが食いたかったのか」
あなたは1番大きなサイズの揚げパンを選んでから、なずちゃんに差し出す。
「ありがと」
店の隅っこに置いてある、端が破れた丸椅子にちょんと座ると揚げパンを頬張り始めた。
私も隣の丸椅子に腰を下ろす。
「美味しい?」
「うん、美味しい」
モグモグと勢いよく食べているけど、少し目が元気が無いように見える。
「ママに連絡しておこうか?」
「それはダメ!ママとケンカしたから。だって、ママは、なずのこと怒ってばっかりなんだよ」
口をとがらせながら、やっぱり揚げパンをパクパクと食べる。
なんて可愛い孫だろうと思わず目が細くなる。
怒ってたって、本当に可愛い。
「なずちゃんが何かしたからママは怒ったのかなぁ」
「違うよ!アレしなさいコレしなさいって、ママはなずのつごうなんて、おかまいなしなんだよ」
「そっか。ママはやってほしいことがあるけど、なずちゃんにもやりたいことがあるのか」
「そうだよ!なずだって真剣にお城を作ってたのに。だから、怒って家出してきたんだよ」
なずは、少し前に買ってあげたレゴのお城セットにまだまだ夢中らしい。
女の子なのにレゴ?と思うけど、なにかのアレとコラボしたお城で、なずちゃんが言うには特別らしい。
家出か。私も小さな家出をしたことがあったんだっけ。
「明日は土曜日だし、今夜はばあちゃん家泊まる?」
「うん、泊まるー!」
「じゃあ、ママに連絡しとかないとね」
なずちゃんはここのお店のお手伝いをするのが好きらしく、足りなくなった商品を並べたりお客さんが来ると「ばあちゃん、来たよー!」と呼んでくれる。
夕ご飯を食べて、なずちゃんと一緒の布団に入る。
「明日は帰る?」
「うん、明日は帰る」
お店に来たときよりも、少しふんわりした顔になっていた。それに、眠そうだ。
「おやすみ」
「おやすみなさい」
子どもの体温は、こんなに温かったっけ?
モゾモゾと動いたと思ったら、クアーーっ!とおおきなあくびをしてから、すぐにスゥスゥと寝息を立て始めた。
規則正しい寝息を聞いていると、急に私も眠気に襲われてそのまま目を閉じた。
あなたはやっぱりゴーゴーともう、いびきをかいている。
目を開くと、高校生のなずちゃんが私を覗き込んでいた。
「ばあちゃん!」
なんで、少し泣いているの?
娘家族と息子家族の顔が皆んな、私を囲んでいる。
隣をみると、小さな写真立てのなかで笑うあなたが見えた。もう、イビキは聞こえない。
そうか。
胸が苦しくなって、そのまま倒れたんだっけ。
いつもの布団が、あったかい。
畳の柔らかさが背中に伝わってくる。
胸が、少し苦しい。
「ありがとう」
なんで、この言葉が出るんだろう?
ようやく言えた言葉にほっとして、また眠くなる。
もうすぐ、約束が果たせるのかしら。
目を閉じる直前、なずちゃんの顔が見えて、やっぱりなんて可愛い孫だろう・・
と思いながら、静かに目を閉じた。
どれくらい眠ったかしら?
幾分すっきりした頭で、目を覚ます。
6畳くらいの暗い部屋の中を、裸電球くらいの柔らかな光が照らしている。
起き上がって隣を見ると、あなたがあぐらをかいて座っている。
「遅かったな」
「あなたが早すぎるんですよ」
「来ないんじゃないかと思ったよ」
「だって、約束したじゃないですか」
「約束?」
「一緒の墓に入ってくれないかって、プロポーズの言葉だったじゃないですか」
「あぁ・・そんなことも言ったかな」
「言いましたよ。あの頃はなんてプロポーズだろうってビックリしましたけどね」
「そうか」
あなたは少し照れて、少し笑った。
「荷物は持ってきたか?」
「ええ、ほんの少しですけど」
最低限の着替えと手帳が入った、小さなボストンバッグ。
「これから色々手続きが必要なんだ。俺が教えてやるから・・」
言い終わるかというところで
荷物をひょいと持ち上げて、サッサと歩き出す。
慌てて追いかけても、早足だから5歩も6歩も先を歩いている。
そうだ。
これが原因で若い頃に何度も喧嘩したんだっけ。
思い出して、くすくす笑う。
「まったく変わらないな。遅いぞ」
そうか。
私が死んでも、思い出は死なないんだ。
ほっと、安心する。
部屋だと思っていたそこは、一方が道になっていた。
街灯がぽつぽつと、遠くまで続いている。
「これから色々とやることがあるからな」
「そうなんですか。ふふ、楽しみですね」
「楽しみか?」
前を向いて、また早足で歩き出すあなたの後ろを歩くのはいつぶりだろうと思いながら
私もならって
街灯の下をゆっくりと歩き出す。