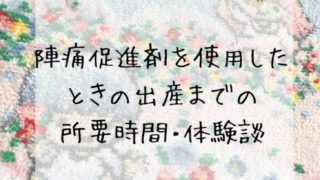僕がこのカフェで働き始めたのは、1ヶ月くらい前になる。
接客係が2人、シェフは1人しかいないカフェ。接客係の人が就職が決まりバイトを辞めるとのことで、【バイト募集】のささやかな張り紙をたまたま見つけたのだ。
仕事を25歳で辞めた僕は、宙ぶらりんになってしまっていた。実家に住んでいるから、働かなくても最低限の衣食住には困らない。でも、生活費くらいは家に入れておきたい。バイトをして、本当にやりたいことをのんびりと探そうと思っていたところだった。
そんな成り行きで働きだした、カフェ兼レストラン。
働くまで知らなかったが、シェフは高級レストランで5つ星をとった経歴もあるらしい。シェフを務めて35年。「そろそろ落ち着いて働きたい」と作ったのが、この小さなカフェらしい。
昼間は学生も出入りする賑やかなカフェになるが、コーヒーを専門に出している店だからフードメニューは毎日日替わりで1種類だけ。今日はハムとロメインレタスのサンドウィッチだった。
夜になると、予約制のレストランになる。
窓一面に贅沢にステンドグラスが貼られているから、外の街灯から漏れる灯りで小さな店内はしっとりと輝く。そのレストランは、シェフと知り合いの人だけが予約をして、時々やってくるといった調子だった。
「今日は20時に美紀さんがいらっしゃるから、よろしく頼むな」
僕がカフェタイムを終えて賄いを食べていると、シェフから声を掛けられた。カフェタイムと賄いの時間を終えて、シェフと一緒に一通り掃除をするのはいつものことだけど、今日は特に念入りに床がひかるまで磨きあげた。
20時を少し過ぎて、入り口のドアは開いた。
「こんばんは」
小さな声でこちらを見上げる女性のあまりの美しさに、僕は声を失いそうになるのを、堪えた。
「いらっしゃいませ。お席へご案内致します」
7cmほどのピンヒールを小気味良く鳴らして、後ろを付いてきてくれているのがわかる。
歩き方がぎこちなくなっているかもしれない。声が上ずっているかもしれない。
席へご案内して、柔らかな素材のコートをお預かりすると、深いブルーのワンピースを着た女性は静かにスツールにこしかけた。5月にはまだ早くノースリーブを着ていて、腕の白さは仄暗い店内で光っているみたいだった。
予約の時点でメイン料理は伺っていたが、飲み物のメニューをお待ちする。
「シャンパンで」
ちらりとメニューに目を向けてから、こちらを見て微笑んだ。
僕はそのまま後ろへ倒れ込みそうになる。
「承知しました」と答えて、努めてゆったり歩くように心掛けながら、席を離れた。カウンター席からは調理場の中の様子が見えて、シェフはもう前菜をほとんど作り終えていた。美紀さんは眩しそうに、シェフの手元を眺めていた。
「失礼いたします。お飲み物をお持ちしました」
絶対に失敗できない。こぼすなんて、ありえない。そう思うほど、手が小刻みに震えてしまう。細い細いシャンパングラスに、慎重にゆっくりとシャンパンを注いでいると、美紀さんは息だけで笑った。
「大丈夫よ」
今度は、子どもに向けるような優しい笑顔を見せてくれた。
「はい、すみません」
ゆっくりゆっくりシャンパンを確実に注いで、ようやく僕は落ち着けた。
「ごゆっくりお過ごしください」
「ありがとう」
ビスクスープの前菜を運んでいるときに、いつもの皿よりも一回り小さなことに気付いた。こんな皿、うちのカフェに置いてあったか?前菜もつつがなく運び、美紀さんはスープに少しずつ口をつけ始めた。
そういえば、と店内の温度を少しだけ上げておいた。ノースリーブでは、ひんやりしてしまうかもしれない。シェフと話すでもなく、1人で静かに皿と向き合って、ゆったりと食事をとる姿は、いつか観たフランス映画のようだと思った。
姿勢は崩れることなく、膝丈のワンピースから伸びたふくらはぎのラインはゆるやかで繊細なカーブを描いている。ステンドグラスの揺らめく光の中で静かに食事をとる、白く煌る女性と「近づきたい」とか「もっと話したい」とか、そんな気持ちは湧いてこなかった。
ただ、このまま見ていたい。
絵画にできたら、いいのに。
と、僕は少し離れた場所から、心からそう思っていた。
前菜が終わり、メイン料理をお持ちした。
「たらこのスパゲティです」
やはり、こちらも皿が一回り小さく、パスタも通常の半分ほどかという量。たらこの量も、とても控えめだ。「今夜の試作だから」と、僕も先ほど賄いで食べさせてもらっていた。素材のたらこの旨味はもちろんのこと、塩味も、かかっているソースも絶妙に美味しかった。
スパゲティを一口、口に運んだ美紀さんは顔をあげて
「美味しい」
とシェフに話しかけた。
「ありがとうございます」
シェフの頬が、少しだけゆるんだ。
上品に少しずつ、とても美味しそうにスパゲティを食べ進めている。
「なぜ、たらこのスパゲティなんですか?珍しいなと思いまして」
シェフは静かに洗い物をしながら、美紀さんに話しかけた。
「ふふ。母が小さなころ、よく作ってくれたんです。たらこがごろっと乗ったスパゲティ。大人になると、なかなか食べられないものだなと思ったので」
美紀さんが話すと、イヤリングが静かに光る。
「そうでしたか」
納得したように、洗い物をする手元に視線を落とした。
「シェフは?思い出の料理って何かありますか?」
洗い物をしていた手が止まった。ほんの一瞬、間を置いて話しだした。
「僕は、幼いころ祖母に育てられたんです。両親は仕事が忙しくて、会えても月に2〜3度でした。寂しさを紛らわせるために、小学生のころ僕はサッカーに没頭していました。
小学校のサッカークラブで初めて大会でレギュラーが取れた時、祖母が応援に来てくれたんです。でも、結局良いところは全然見せられなくて、チームもボロ負けでした。
気まずくて、応援に来てくれた祖母に『来てくれてありがとう』って、試合の後に言えなかったんです。その日の夕飯が、すき焼きでしたね。祖母は裕福とはいえない暮らしをしていたので、今思うとかなり無理をしてくれたのかなと思います。
悔しかったのに、肉がたっぷり入ったすき焼きは本当に美味しくて沢山おかわりしてしまってましたね。それから、試験で良い点数を取ったときとか、僕がすごく嬉しかった日や悔しかった日にすき焼きを出してくれるようになりました。
それが、思い出の料理ですかね」
「すごく、素敵ですね」
「今でも、時々食べたくなるんですよね。独り者だからすき焼きなんてって思うんですけど、年に1回くらいは嬉しいことがあった日に食べることにしてるんです」
「それなら、今度のすき焼きの時には是非呼んでください」
「いえ!そんな、恐縮です。そんな……」
頭に白いものが混じったシェフの顔が、遠く離れたこちらからでもわかるくらいに赤く染まった。
側から聞いていて、本気なのか冗談なのか、僕にもわからなかった。
デザートの小ぶりなりんごのシャーベットをお出しする。この銀の細いスプーンも、今までに見たことがなかった気がする。これも賄いで食べさせてもらったものだ。りんごの果肉をそのまま感じるようなやさしい甘さのシャーベット。
静かにデザートまで食べ終え、スツールから降りた美紀さんにコートをお渡しする。
「ありがとう」
指先は細く、白い指にはリングはひとつもはめられていなかった。その代わりに華奢な腕時計を1つしている。
カードで会計を済ませると、シェフも見送りに調理場から出てきた。
「ご馳走様でした。とても美味しかったです」
「ありがとうございました。是非、またお越しください」
優しい穏やかな微笑みを残して、静かに美紀さんは店を後にした。
夢のような時間だったなとボンヤリしていると「ふううう」と、大きなため息にも似たような声が隣から聞こえた。
「今度は、すき焼きを練習しておかなきゃな」と
ぼそりとシェフがもらした。
**あとがき**
「ケイゾク」を見てから、ずっと中谷美紀さんの大ファンです。
あんな素敵な大人の女性になりたいなとずっと憧れ続けていましたが、そうはいかないものだなと大人になった今、ちょっと残念に思っています。
一人でレストランで食事を楽しむという話をどこかで耳にしたことがあったので、創作で中谷美紀さんのワンシーンを書いてみました。
今回も、3000文字チャレンジに参加させて頂きまして、ありがとうございます!!